朝ドラ『ばけばけ』、もう観ましたか?
明治から大正にかけて激しく変わっていく時代の中で、ひとりの女性が“化けるように”成長していく姿が話題を呼んでいますね。
実はそのヒロインには、実在のモデルがいます。

続きを見る
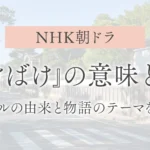
NHK朝ドラ『ばけばけ』の意味とは?|タイトルの由来と物語のテーマを紹介
この記事でわかること
- 『ばけばけ』ヒロインのモデルは実在した人物
- 『小泉セツ』の人物像
目次
『ばけばけ』ヒロインのモデルは実在する?
出典:NHK
朝ドラといえば、これまでも『らんまん』『ブギウギ』『おちょやん』など、実在の人物をモデルにした物語が多く制作されてきました。
このような流れからも、『ばけばけ』のヒロインも「誰がモデルなの?」と注目が集まっています。
そしてそのモデルといわれているのが、「小泉セツ」という女性です。
彼女は、当時まだ女性が表立って社会進出することが珍しかった時代に、教育や芸術の分野で才能を発揮し、多くの人に影響を与えた人物。
史実を再構成したオリジナル脚本ではありますが、『ばけばけ』のヒロイン像の“芯”には、この小泉セツの生き方が息づいているのです。
小泉セツとはどんな人物だったのか
 ここからは、ヒロインのモデルとされる小泉セツがどんな女性だったのかを見ていきましょう。
ここからは、ヒロインのモデルとされる小泉セツがどんな女性だったのかを見ていきましょう。
彼女は「怪談」で知られる小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻であり、夫の日本文化理解を支えた人物として知られています。
しかしその人生は、単なる“偉人の妻”では語り尽くせません。
貧困や差別、そして時代の制約を乗り越えて生きたその姿は、まさに『ばけばけ』のヒロイン像に重なる“実話の原点”といえるのです。
小泉セツの基本情報
小泉セツ(節子とも記される)は、慶応4年(1868年)2月4日に島根県松江市で生まれました。
生年月日については資料によっては2月26日とされることもあります。
1932年(昭和7年)2月18日に没。享年64歳でした。
出身は松江藩の士族・小泉家。父は小泉弥右衛門湊、母はチエ。
母方は松江藩家老職の塩見家の出身という説もあり、武家の娘として生まれながらも激動の時代に翻弄された女性でした。
幼少期|士族の家に生まれ、養女として育つ
セツは、生まれてわずか7日目で稲垣家に養女に出されています。
小泉家と稲垣家は縁戚関係にあり、かねてから「次に子が生まれたら養子に出す」という約束がありました。
養父母・稲垣金十郎とトミは、士族出身のセツを「お嬢(オジョ)」と呼び、まるで実の娘のように愛情を注ぎました。
稲垣家は教育熱心で、セツも自然と学問に親しむ環境で育ちます。
この養家での温かい愛情と、士族社会に見られる厳しいしつけの両方が、のちに彼女が持つ“芯の強さ”や“礼節を重んじる人柄”を形づくっていきました。
学問を好む少女、そして家計を支える現実
幼少期から成績優秀だったセツは、文字の読み書きだけでなく、
手先の器用さや観察眼にも優れた少女でした。
しかし、家計が苦しく、わずか11歳で小学校を卒業後、進学を断念。
当時の日本では、女子教育がまだ一般的ではなく、
「女の子に勉強は不要」という社会通念が残っていました。
それでもセツは読書をやめず、仕事の合間にも書物を開いては学び続けたといいます。
貧困や社会の壁に阻まれながらも、“知ること”を諦めなかった少女。
この姿勢は、『ばけばけ』のヒロインが描かれる「変わる勇気」にそのまま重なります。
運命の出会い──ラフカディオ・ハーンとの交流
1891年(明治24年)、セツの運命を大きく変える出会いが訪れます。
英語教師として松江に赴任していたラフカディオ・ハーン(のちの小泉八雲)との出会いです。
当時のセツは、生活のために働く中で、ハーンの家に住み込みの家政婦として雇われました。
英語が話せなかったセツでしたが、身振り手振りで懸命に意思を伝え、
日本の文化や家庭のあり方を、日常を通じてハーンに教えていきます。
ハーンは次第に彼女の誠実さ、優しさ、そして“静かな知性”に心を惹かれていきました。
やがて二人は深い絆を結び、1896年(明治29年)2月に正式に結婚。
ハーンは帰化し、「小泉八雲」と名乗ってセツの戸籍に入夫します。
この結婚は、当時としては極めて珍しい国際結婚でした。
言葉も文化も違う二人が、互いを尊重しながら共に生きる姿は、
まさに“境界を越えて化ける”生き方そのものでした。
八雲を支えた「影の共作者」
小泉八雲の作品には、セツが語った昔話や信仰、生活文化が数多く登場します。
彼女は、単なる妻ではなく、日本文化の通訳者であり、八雲文学の原動力でもありました。
「怪談」や「耳なし芳一」など、ハーンが愛した日本的情緒の多くは、
セツが日々の暮らしの中で彼に語り伝えた言葉や記憶から生まれたといわれています。
つまり、八雲文学の根底には、セツという“生きた物語”が息づいていたのです。
『ばけばけ』ヒロインと小泉セツの共通点
朝ドラ『ばけばけ』のヒロインと小泉セツの生き方には、重なるものがあります。
それは「変化の中でどう生きるか」というテーマに貫かれた3つの共通点です。

変わることを恐れず、時代の波に飛び込む強さ
ヒロインが失敗を繰り返しながらも前に進もうとする姿は、小泉セツそのものです。
明治という激動の時代、女性が社会に出ることや自分の意志を語ることは、簡単ではありませんでした。
それでもセツは、自らの手で道を切り開き、外国人との出会いや新しい価値観を受け入れながら、自分を「変えていく」ことを選びました。
ヒロインもまた、「変わる」ことを恐れずに、時代のうねりの中で成長していきます。
その姿は、“化ける=変化する”ことを肯定するドラマのテーマそのものを体現しています。
芸術と表現を通じて、人と社会をつなぐ
セツにとって、絵を描くことや言葉を学ぶことは、単なる趣味ではありませんでした。
それは「人とつながるための手段」であり、「世界を理解するための窓」でもあったのです。
ドラマのヒロインも、芸術や表現を通して自分の想いを形にし、人々の心を動かしていきます。
セツと同じように、彼女は“表現すること”で社会と関わり、他者との違いを受け入れながら成長していくのです。
女性の自立を信じ、「生き方」で示す強さ
セツは、自分の生き方を通して「女性が社会の中でどう在るべきか」を問い続けた人でした。
彼女は特別な言葉で訴えるのではなく、日々を誠実に生きることで、次の世代の女性たちに勇気を与えました。
ヒロインもまた、誰かに従うだけの存在ではなく、「自分の人生は自分で選ぶ」という強い意志を持っています。
「あなたが変われば、社会も変わる」──セツが残したこの精神は、ヒロインの姿にも息づいているのです。
『ばけばけ』が伝える“化ける勇気”

『ばけばけ』というタイトルには、単なる「変化」だけでなく、“成長”や“再生”という意味も込められています。
小泉セツが時代の偏見や限界を越えようとしたように、ヒロインもまた、「環境に負けず、自分の意志で未来を切り開く」姿勢を見せてくれます。
この物語が現代の視聴者に響くのは、私たちが今も「変わりたい」と願いながら生きているから。
セツの実話をベースにしたこのドラマは、時代を越えて“化ける勇気”を教えてくれるのです。
【まとめ】実話を知ると『ばけばけ』がもっと面白くなる
『ばけばけ』のヒロインは、明治から大正期に活躍した小泉セツという女性の実話をもとに描かれています。
彼女のように、時代の流れに抗いながらも自分らしく生きた女性の姿が、現代の視聴者にも強く共感を呼んでいます。
実話の背景を知ることで、ドラマの一つひとつのセリフや行動に新たな意味が見えてくるはず。
これから放送が進むにつれ、ヒロインがどのように“化けて”いくのか──その先に、小泉セツが残した生き方の答えが見えてくるでしょう。

続きを見る
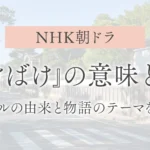
NHK朝ドラ『ばけばけ』の意味とは?|タイトルの由来と物語のテーマを紹介
![]()
